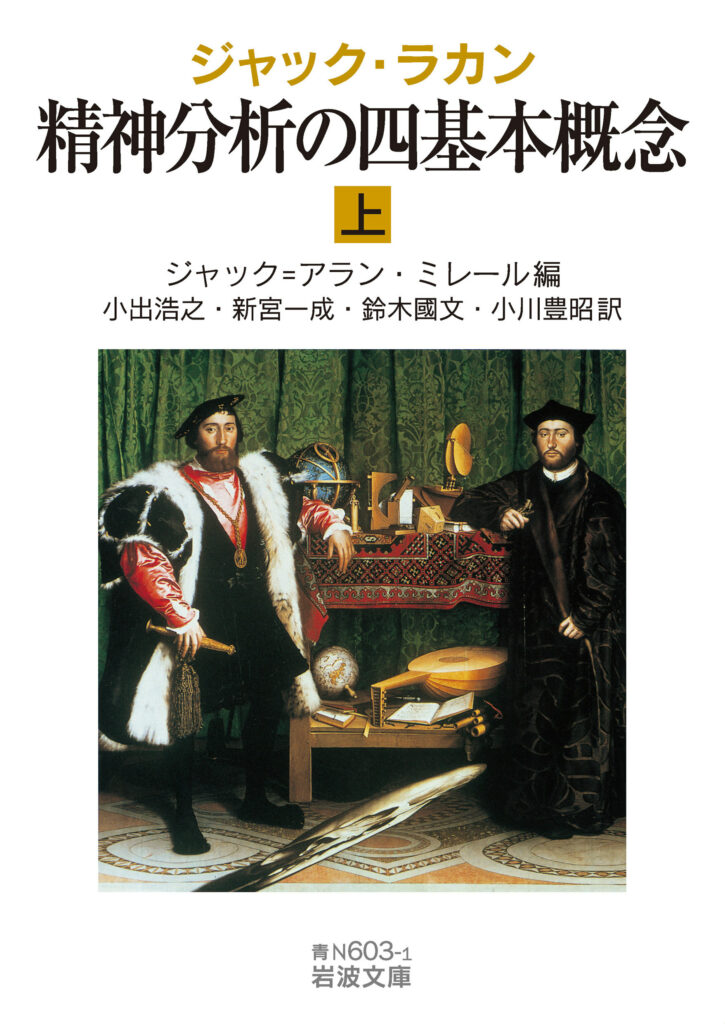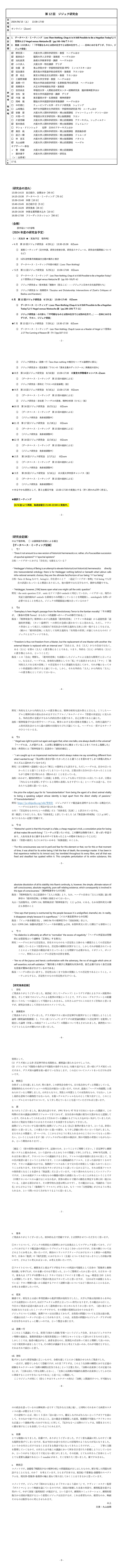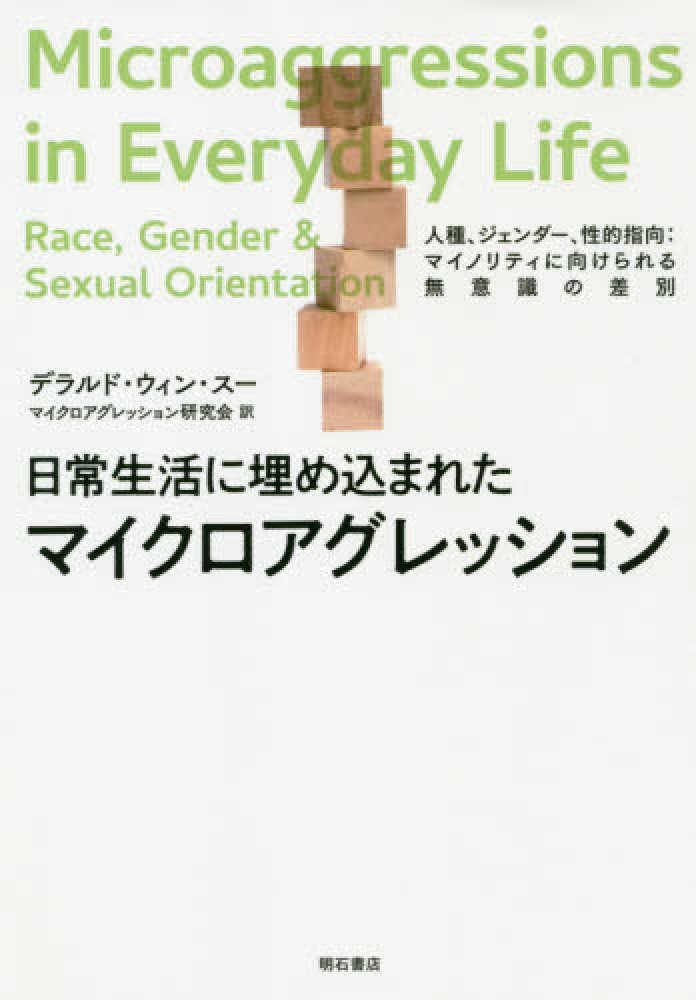「ラカンと現代社会」研究会 7月活動報告
文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)
活動日|7月4、18、25日
参加人数|いずれも6名
7月の研究会では、ラカンのセミネール『精神分析の四基本概念』の第Ⅶ講を読みました。ラカンがホルバインの『大使たち』とダリの作品の親近性について論じているところから、神経症における「眼差し」の経験と精神病(パラノイア)における「眼差し」について議論したほか、質疑応答でのやり取りからサルトルとラカンの「他者」概念の違いを改めて確認しました。
これで漸く第Ⅶ講が終わります。8月は活動せず、9月から第Ⅷ講に入ります。岩波文庫版の上巻だと、残り2講となりました。焦らずゆっくり議論しながら読み進めたいと思います。