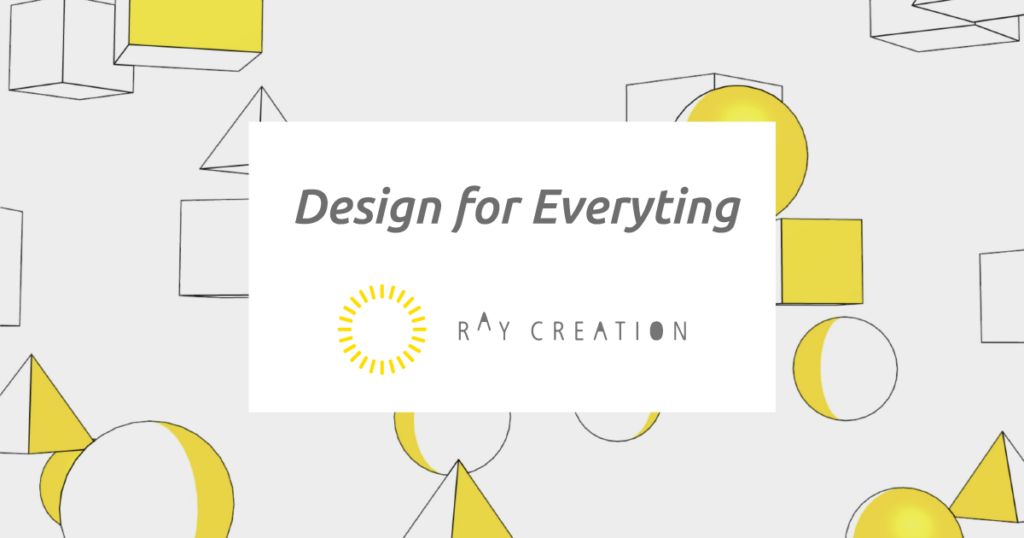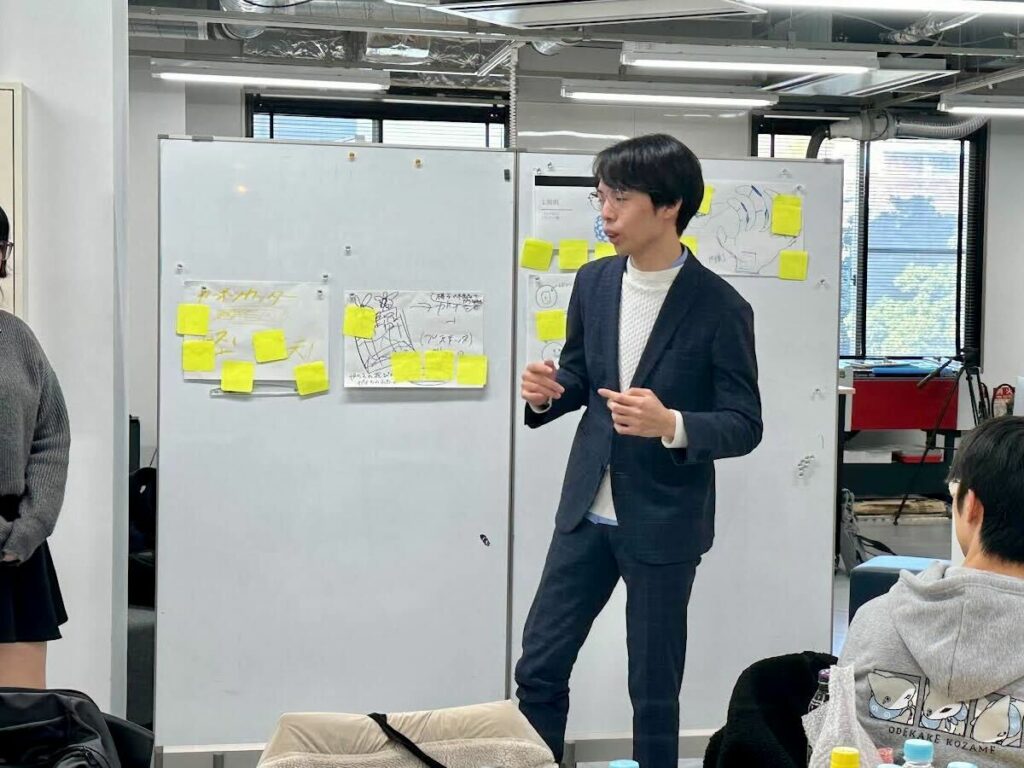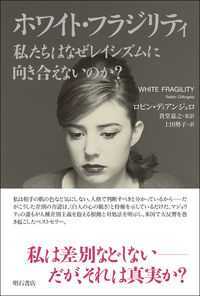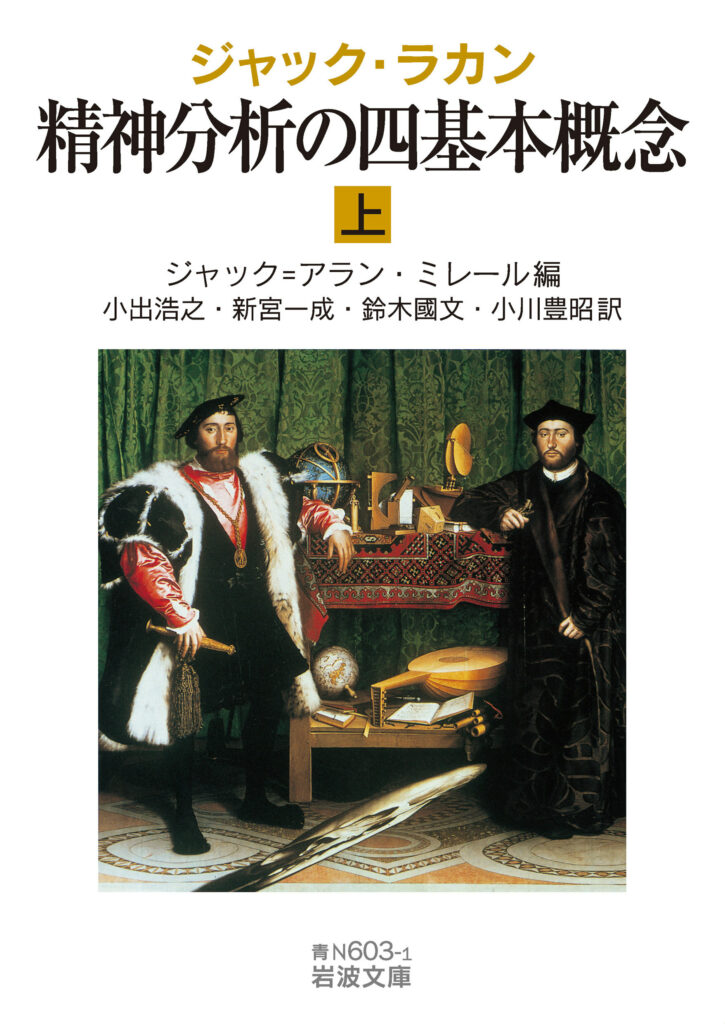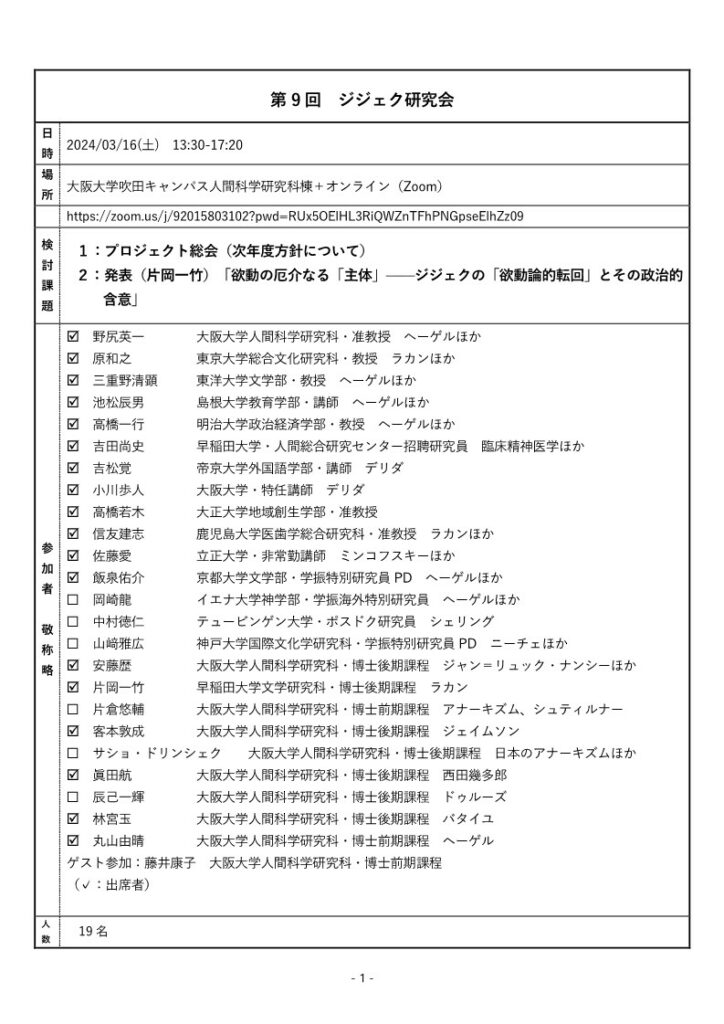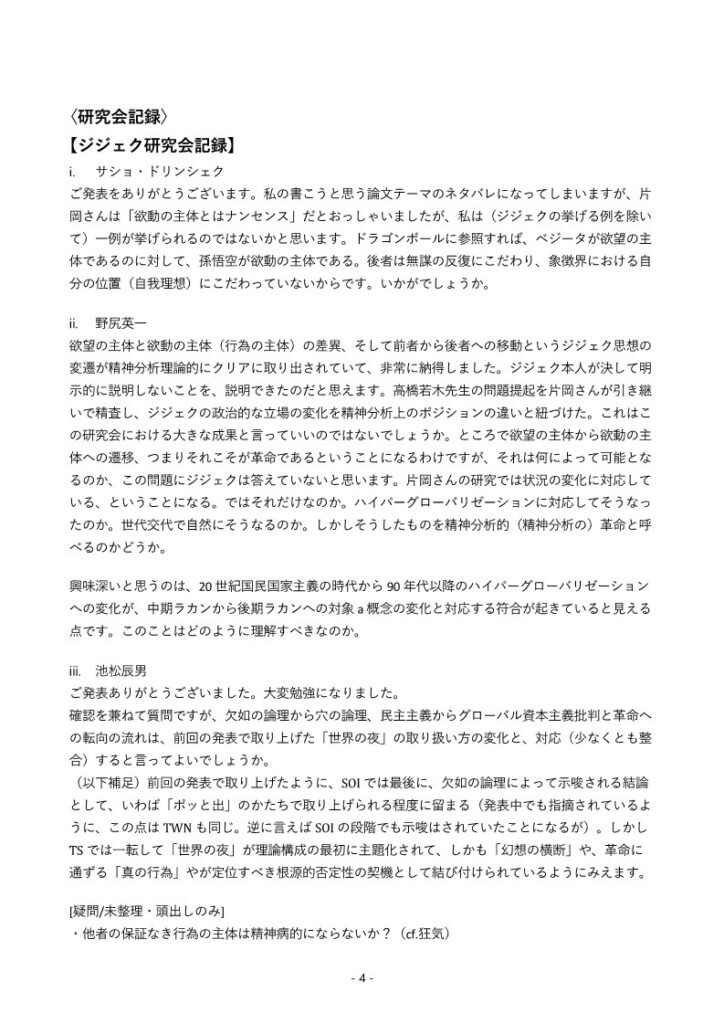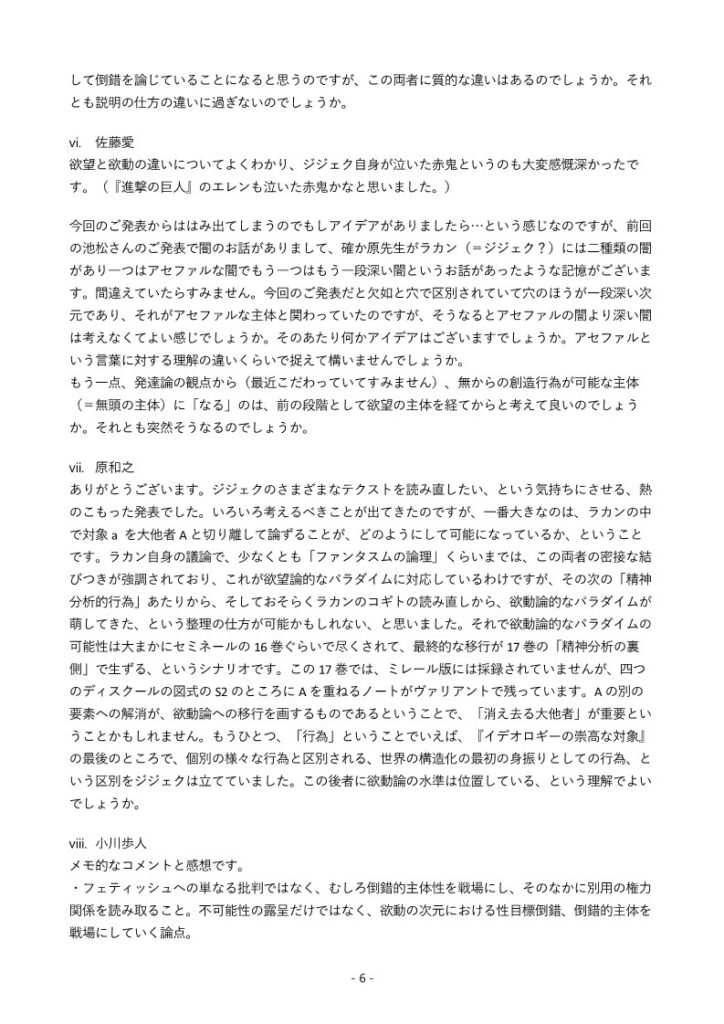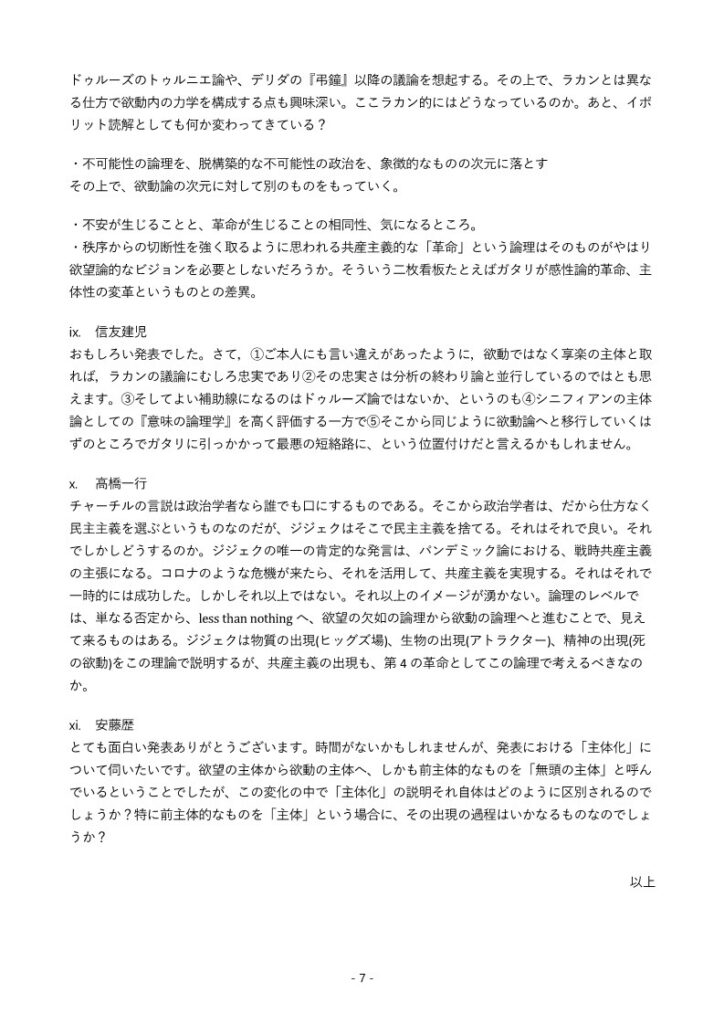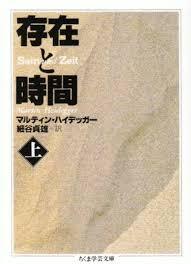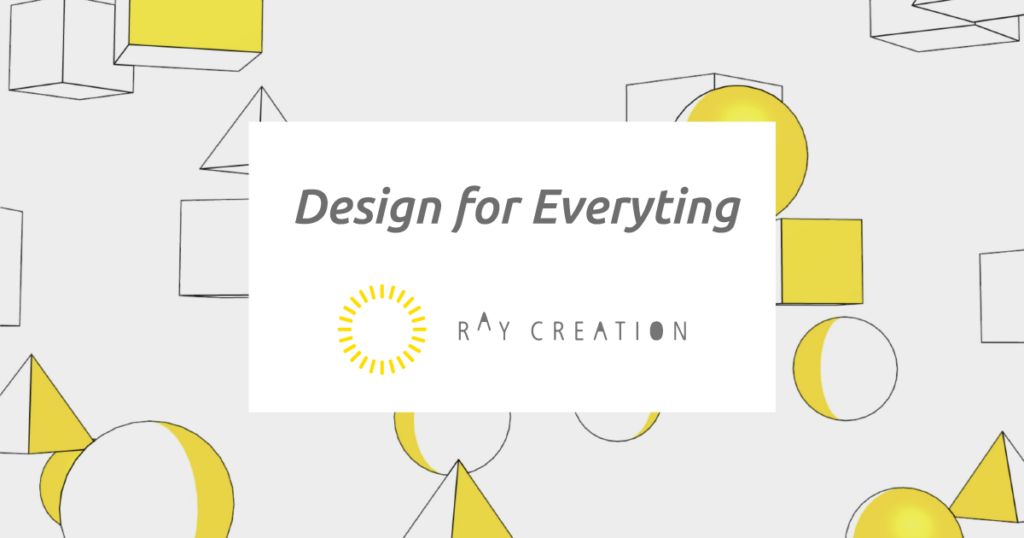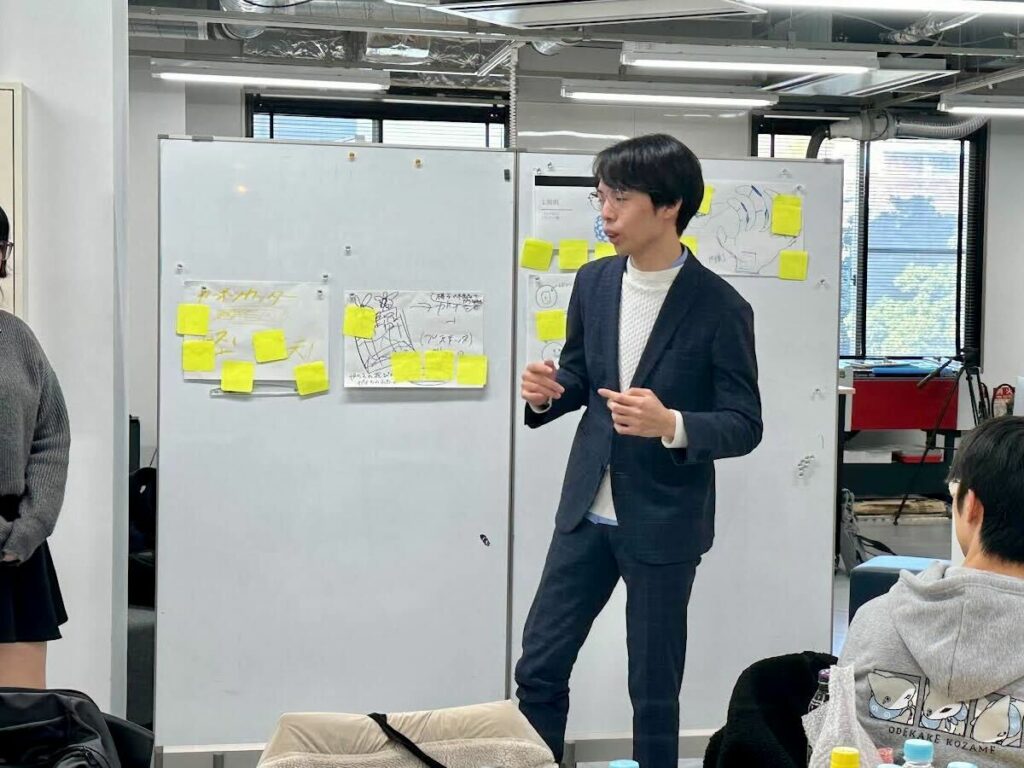丸山由晴(社会学系・比較文明学M2)
2月13日(火)から2月16日(金)
今般、哲学の実験オープンラボ取次のもと、株式会社レイ・クリエーション様※で4日間のインターンシップを行うこととなった。
※大阪市中央区本町4丁目5番7号 サンドール本町8階
レイ様は、エネルギー、医療、工業分野を主軸として、webデザイン、動画制作、広告制作など総合的なプロモーションのデザインを主な事業として展開されている。
私は、インターンシップということで、実際に各事業の企画、折衝、社内打合せ、現場での撮影に参加させていただくこととなった。今般のインターンシップで面白かった第一の点として、いわゆる「インターンシップ」と異なり、実際の業務を見学、さらに参加することができた点だ。ベンチャー企業や技術職としての求人はともかくとして、(学部時代の私もそうであったが)一般に文系の学生が総合職として就職活動を行うとなると、人事部が「就活」向けに設定した「インターンシップ」に参加することなる。そこで行われるのは、実質的には会社説明や他のインターン生とのワークショップであり、言葉本来の意味でのインターンシップは行われない。その点で今回は実際に各種業務に参加することでき、大変勉強になった。
それでは、具体的な学びの内容について報告したい。哲学分野の学生としてビジネスとはいささか距離感があり、今回参加する中でもすぐには適応できない点もあったが、他方哲学分野の学生であるからこそ気づけた点もあった。それは、仕事をするにあたって取ってつけたような外在的な進め方ではなく、目的に応じて物事の内在的な繋がりから考えることがいかに重要であるか、である。
デザインをするにあたって、デザインを単に「綺麗」や「一般的」という理由で構成するのではなく、なぜそのようなデザインであるのかを、顧客の要望や顧客の置かれている状況から、筋を通したものとできるように思考することが重要であると、レイ様の代表、原田社長は会議で語られていた。そうでなければ、デザインは外在的なものとなり、そのデザインである理由を説明することも顧客に対する訴求力を発揮することもできないと。またデザインの考案以外にも、事情方針についての社内会議にも出席させていただいたが、そこでも事業計画や具体的な事業を立案するにあたって、目標に対してなぜその構成、内容であるのかを説明できる論理が求められていた。私自身の言葉で言い換えれば、総合してビジネスにおいても、目的に対する必然的な論理が求められているのだと理解できた。必然的というのは、他ではなくそれである事由を具えているということだ。
もちろん、特にレイ様がデザインを事業にされているがゆえに、その傾向が強いのだろうが、しかしビジネスにおいても物事を進めるにあたって、確かな根拠と必然的な繋がりがなければ、自身の行うことは他者に対して訴求力を持ちえないのだと理解できた。
さて何故あえて、「哲学分野の学生として」という言葉を始めに付けたのかと言えば、それは自分自身が普段テキストを読み、研究発表をする中で、内在的な必然性を伴った論理こそそれらの要であると、ぼんやりと考えていたからだ。「ぼんやり」と書いたのは、今回インターンシップに参加することで、分野を問わず重要な事柄であると、反省的に認識し、自分自身の研究に関しても重要な事柄である明確にすることができたからだ。考えてみれば当然のことであり、それだけ私が世間のことを知らない証左であるのだが、しかし物事を考えるにあたっては研究と仕事で決定的な隔たりはないと気づけたのは、私にとって大きな学びであった。
以上のほかに、レイ様が加盟されている株式会社 大阪ケイオスの定例会などの企業の集まりにも出席させていただいた。普段触れることのない、大阪の中小製造業の方々から、また自分の知らない世界ややり方について学ぶことができた。
末筆ながら、歳末も近くお忙しいところ、今回インターンシップ参加をご快諾いただいたレイ・クリエーション様には、御礼申し上げます。
以上