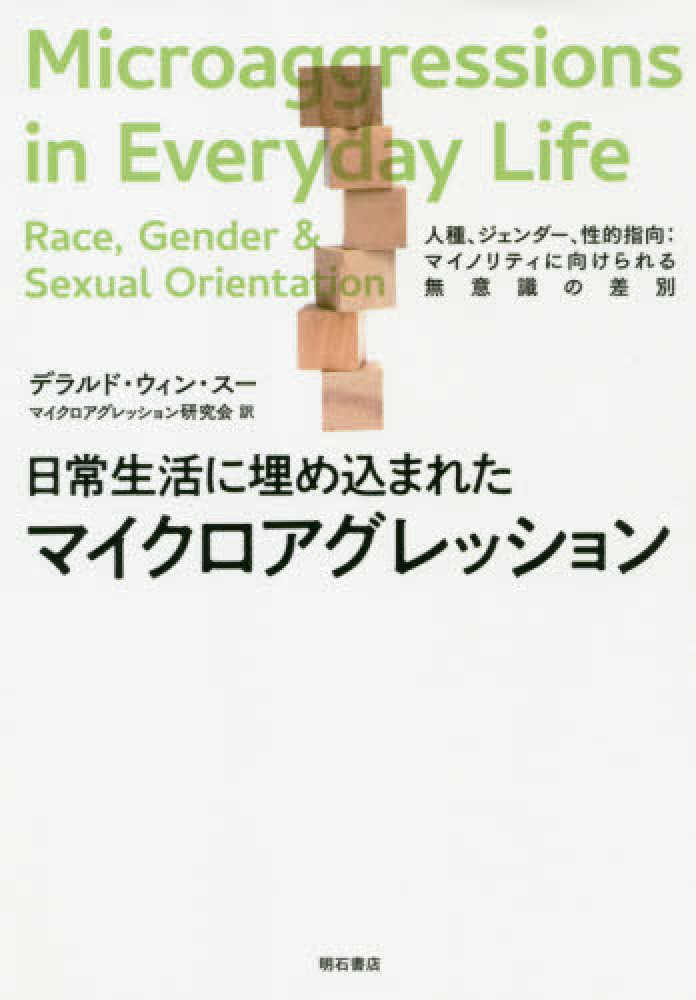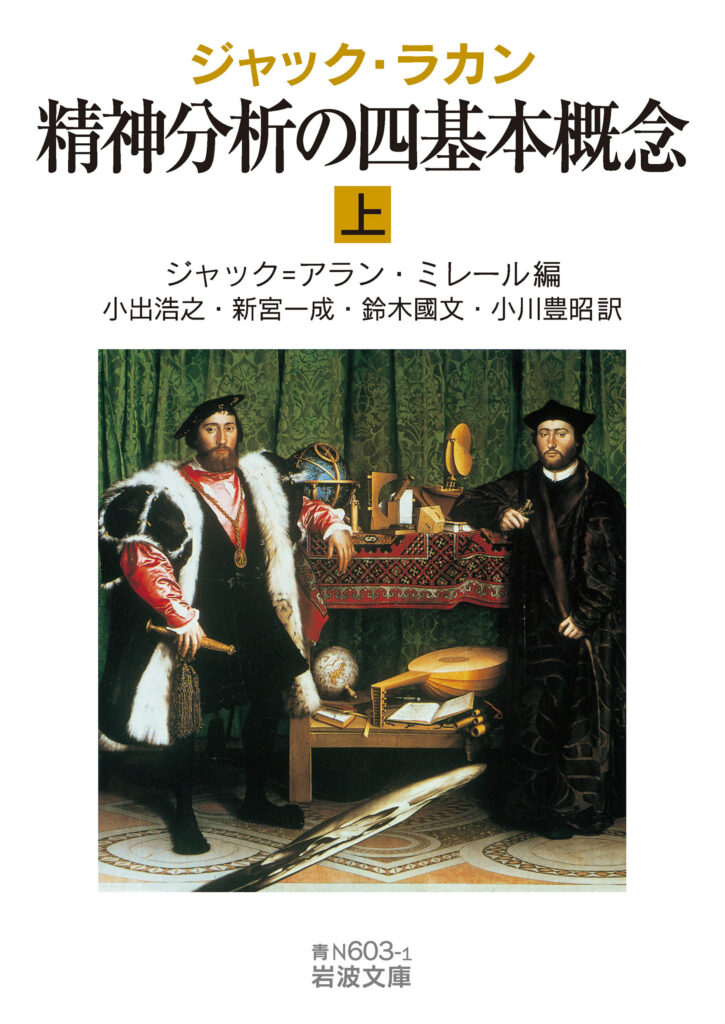マイクロアグレッション関連文献読書会 10月活動報告
文責:客本敦成(社会学系・比較文明学)
活動日:10月23日
今月も引き続き、デラルド・ウィン・スーの著作『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション』の読書会をおこないました。今回は第11章の読書会をおこないました。
第11章では、主に教育におけるマイクロアグレッションが扱われていました。参加者に教育学を研究するメンバーがいたため、日本の状況と比較しながら議論することができました。特にスーの著書ではそれほど議論されていなかった、教育を巡る制度的状況について注目することができたと思います。
11月も引き続き『日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション』を読み進めます。
また来年1月からはロビン・ディアンジェロの『ホワイト・フラジリティ 私たちはなぜレイシズムに向き合えないのか?』(日本語訳は明石書店)を読み進めることになりました。
いずれの読書会も新規参加者を募集しています。ご関心ある方はお気軽にご連絡ください。