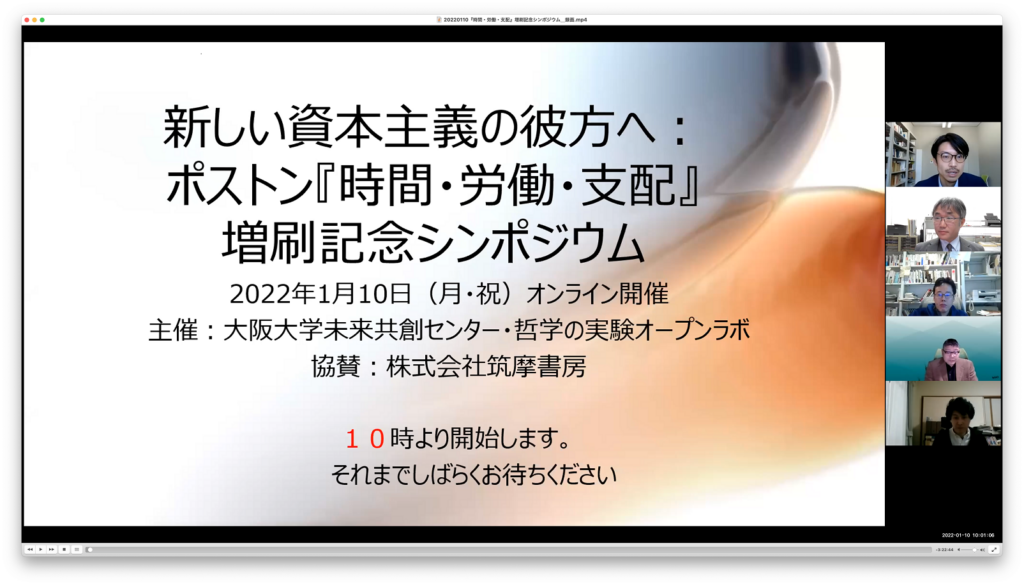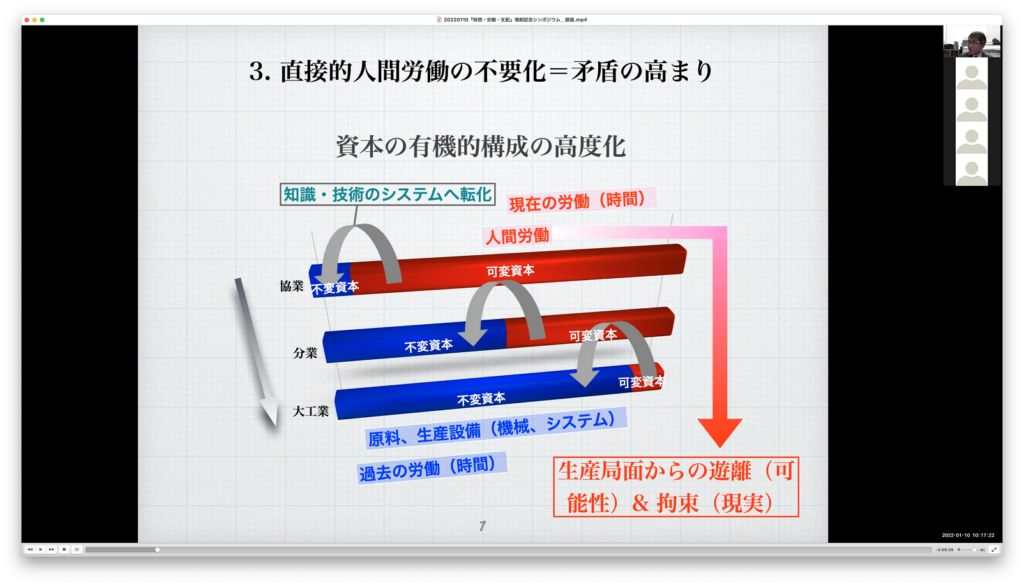美的近代研究プロジェクト 第二回読書会報告
2022年1月30日に実施された、哲学の実験オープンラボの公認プロジェクトの読書会です。以下は参加された学生の報告です。
文責:安藤歴(共生学系・共生の人間学)
1月30日(日)
美的近代研究会メンバー8人参加
今回は、ユルゲン・ハーバーマス『近代未完のプロジェクト』に所収されている「近代未完のプロジェクト」という講演録を読みました。この講演録は、アドルノ賞受賞記念講演であり、アドルノのモデルネ論を引き継ぎつつも、「モデルネというプロジェクト」を「止揚のプログラム」ではなく「啓蒙のプログラム」として擁護しようとするハーバーマスの立場を確認しました。同時代の議論に対するハーバーマスの批判やカント読解、文化的伝統の意義付けなど、様々に議論を行いました。
次回は、2月15日19時から、神戸大学准教授の石田圭子さんをお呼びして、「ファシズムと崇高」というタイトルでお話しいただく予定です。