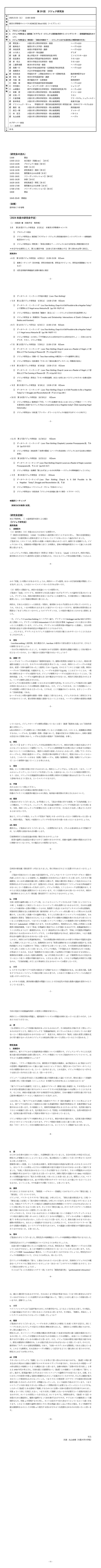第20回ジジェク研究会
第20回ジジェク研究会
日時:2025年3月15日(土) 13:00〜18:00
場所:東京大学駒場キャンパス(ハイブリット)
参加人数:18名
プログラム
- プロジェクト総会
- ジジェク研究会a:眞田航「スラヴォイ・ジジェクと西田幾多郎のミッシングリンク——欲動論的転回をめぐって」
- ジジェク研究会b:野尻英一「革命か和解か?——ジジェクにおける否定性と無限判断の行方」
概要報告
3月の研究会では、プロジェクト総会とInternational Journal of Žižek Studies誌論文投稿にむけての研究発表が2件なされた。プロジェクト総会では、プロジェクト2年度目の締めくくりとしてこれまでの総括と、次年度以降の活動内容・日程についての協議がなされた。
研究発表では、まず眞田氏(大阪大学大学院)から西田幾多郎とジジェクの比較研究が発表された。
本プロジェクトメンバーでもある高橋若木氏によれば、ジジェクには、象徴秩序、言語の存在を前提し、そこからアクセス不可能なものを「欠如」と捉えていたところから、この不可能なもの自体が現実を構成すると捉えるに至る、哲学原理と政治思想の変化をめぐった「欲動論的転回」が存在する(※1)。
これを受けて眞田氏の発表では、西田において不可能なものを指す概念「絶対無」が、単に象徴秩序、言語、哲学の側からアクセス不可能なものから、『無の自覚的限定』以後反対に現に存在することによって意味の秩序の存在が論じられるようなものへと、ジジェク同様に転回していったとされる。
質疑応答では、西田の皇室論や絶対無への非哲学的アクセスという点でのシェリングからの影響、ジジェクと西田を比較するにあたっての政治思想の違いなどが議論された。
※1:高橋若木(2022)「ジジェクの転回【欲望と欲動】」『社会思想史研究』(46),168-185.次にプロジェクトリーダーである野尻氏(大阪大学)が、ジジェクにおいて「想像的なもの」や「未来」への「想像力」の役割が希薄なところを切り口に、ジジェクが依拠する哲学者であるヘーゲルにおける想像力(構想力)の役割に遡りつつ、野尻氏が読むところのジジェクの現状に対する答えとは別の答えを模索する研究構想を発表した。野尻氏によれば、ジジェクはラディカルな革命論を論じているようで、実のところ(一般に理解されるヘーゲルと同様)哲学的にも政治的にも現実との「和解」を示している。これに対して野尻氏は、ジュディス・バトラーの主張も参照しながら、非資本主義的(=非現況的)想像力とそれによる変革の可能性を構想している。
質疑応答では、ラカンやヘーゲルにおける体系外への開放性のほかに、研究構想が現代日本国家論も射程に収めることから、東アジアにおける「和解」の可能性やその際の「和解」とヘーゲル=ジジェク的和解との相違などが議論された。議論や実施内容の詳細は添付資料を参照のこと。
※科学研究費基盤B(23H00573)「スラヴォイ・ジジェク思想基盤の解明:ヘーゲル、ラカン解釈を中心に」研究代表者・野尻英一
文責:丸山由晴(比較文明学)