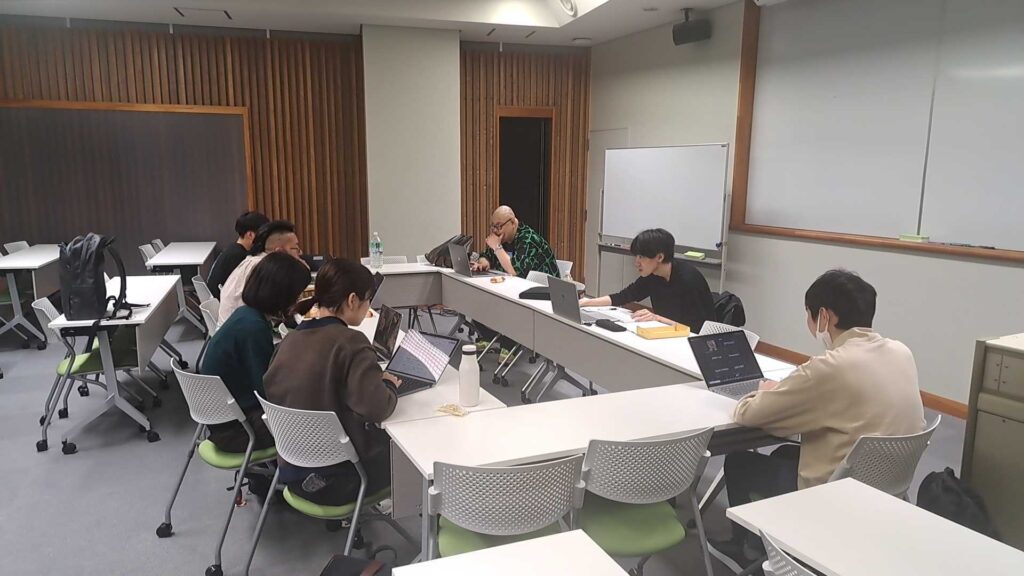現代思想研究会 2024年11月-2025年4月 活動報告
活動日|2024年11月6日、13日、25日、12月19日、2025年2月5日、3月24日、4月11日
文責|客本敦成(比較文明学)
2024年11月は、10月に予定されていたものの延期になっていた研究発表を2件おこない、定期報告を1件おこなった。また勉強会として、ジャック・デリダ『アデュー』の読書会をおこなった。
11月6日には、布施哲朗氏と池田信虎氏による研究発表をおこなった。
布施氏の発表はエマニュエル・レヴィナスの『全体性と無限』における享受概念を扱うものであった。近年の自我論に注目する研究動向を踏まえつつも、享受概念を単に対象に没頭することではないものとして解釈することで、自我論の別の側面が示された。
池田氏の発表はガストン・バシュラールとジョルジュ・カンギレム、およびミシェル・フーコーの比較を追うことで、「合理性」という論点が浮かび上がることを示すものであった。三者による理性および合理性の位置を比較することで、特にバシュラールの合理性概念の位置のユニークさが明らかになった。
11月7日には、客本敦成(大阪大学)による研究発表をおこなった。ジャック・ラカンが提示する「ラメラの神話」を欲動論として分析することで、言説の水準ではなく、身体器官の水準でラカン的な主体性を提示できることを示した。
11月25日には、ジャック・デリダのレヴィナス論『アデュー』の読書会をおこなった。レヴィナス研究者の藤本崇史氏(早稲田大学)と松村健太氏、デリダ研究者の小川歩人氏および櫻田裕紀氏(早稲田大学)にも参加していただき、デリダによるレヴィナス解釈から、両者の問題意識の違いや重なりがどのようなものであるか、議論された。
12月19日には、曹思敏氏と板野文記氏による研究発表をおこなった。
曹氏の発表は、日本と中国における男性同性愛表象の作品(日本の「ボーイズ・ラブ」、中国の「耽美」)を、ジャック・ラカンおよびスラヴォイ・ジジェクの精神分析理論を援用しながら検討するものであった。理論的考察と作品分析の関係など、内容だけでなく、方法論や議論の構成についても話題が及んだ。
板野氏による発表は、アンリ・ベルクソンの「社会」についての議論を、ベルクソンの諸著作を横断しながら検討するものであった。『笑い』を出発点としつつ、『意識に与えられたものについての試論』などの他の著作も検討することでベルクソンの議論を整理し、ベルクソンの「社会学」を提示することが試みられた。
2025年2月5日には、池田信虎氏と林宮玉氏による研究発表をおこなった。
池田氏の発表は、フランス・エピステモロジーの研究者であるAnastasios Brennerの諸著作についてのサーヴェイ発表であった。Brennerはオーギュスト・コントやアベル・レイといった、いわば「前史」からフランス・エピステモロジーの歴史を描きつつ、同時に英語圏やドイツ語圏の議論との対応関係を指摘する研究者である。池田氏はBrennerの様々な研究を要約したうえで、エピステモロジーがそなえる哲学との緊張関係の検討を今後の課題として指摘した。
林氏の発表は、ジル・ドゥルーズの『ザッヘル・マゾッホ紹介』の分析であった。林氏は、20世紀を代表するヘーゲル研究者であるジャン・イポリットのフロイト論におけるdénégation概念を、ドゥルーズが意味をずらして使用していることを指摘しつつ、両者がいずれもこの概念をヘーゲル哲学に結び付けながら議論を展開していることを指摘した。そのうえで、ドゥルーズの「法」についての考察が、ラカン的な「父の名」についての議論を欠いているのではないかという疑問を提示した。
3月と4月には、日本学術振興会特別研究員への応募にかんする活動をおこなった。
まず3月4日には、池田信虎氏による、特別研究員PD応募書類についての報告をおこなった。他大学からの参加者も積極的に議論に参加し、有意義な情報交換をおこなうことができた。
また4月11日には、コメンテーターとして小川歩人氏(日本学術振興会特別研究員PD、元日本学術振興会特別研究員DC2)をお招きし、山本昇弥氏(大阪大学)と雪丸温翔氏(大阪大学)を報告者としたうえで、応募申請書の検討会をおこなった。こちらも充実かつ綿密なコメントがなされ、充実した検討が行われた。